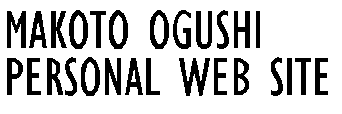
10月16日号 『社用車で来た娘』
その昔、高木虎之介が有望な新鋭レーシングドライバーとして注目を浴びた頃、とある新聞社系週刊誌の女性記者がわたしに電話をしてきた。用件がすさまじかった。「先日、高木選手に取材したのだが、ほとんど記事になるようなことを聞けなかった。ついては国内レース界で高木選手を繰り返し取材している大串さんに取材して記事を作り直したい」というのだ。
確かに、当時の高木は取材慣れしておらず、おまけに人見知りで、初対面のしかもわけのわからないままやってきたオヤジ週刊誌の記者にまともな対応はしなかったに違いない。わたしですら、最初にインタビューしたときには「モゴモゴ」とほとんど聞き取れないような声でしか話そうとしない高木に往生した。それどころか、自分は彼が言語に障害を持っていることを知らずに強引で無礼な取材をかけてしまったのではないか、と一瞬慌てたものだ。
そんなことがあったものだから女性記者の陥った苦境も理解できた。しかしわたしに取材して高木のインタビュー記事を作り直すというのはいかがなものか、と首をひねりはした。そもそも、そういう目的の取材にホイホイ対応していいものだろうか、と。だがとにかくわたしの仕事場に行く、と女性記者は言い張る。まあ、わたしも若い女性は嫌いではないから、じゃあまあとにかくお話だけでもしましょうと、申し出を受け入れた。
その後、彼女はわたしの仕事場へやってきた。年の頃二十代半ば、大学を出てそのまま週刊誌編集部の配属になったとおぼしき娘だった。「クルマで来ましたか?」と聞くと「そうだ」というので、「それなら向かいのスーパーマーケットの駐車場に入れちゃえばいいですよ」と、インチキ駐車法を教えると「いえ」と彼女は拒絶する。はて、ずいぶん潔癖な娘だな、これじゃ下手なことはできないなくらいのことを思ったわたしは、次のセリフを聞いてひっくりかえった。「社用車ですから運転手が待ってます」
そうか、そういうことか、とわたしは萎えた。新聞社系週間誌の女性記者は、社旗を立てた社用車でこんなしがないライターの取材にやってきたのか、と。要するに、おそらくは一回り以上も年上のオヤジより、ずっと待遇がいいんじゃん。というより、ずっと偉いんじゃん、と。
がっくりきたわたしは、その後まるで自白剤を打たれたうえで尋問を受けるスパイみたいに無抵抗になって女性記者の取材を受けたのだった。どんな記事になったのか、忘れてしまった。確か、モータースポーツライターの大串氏いわく、式の記事にまとまっていたのではなかったか。そして後日、予想もしなかった取材謝礼が1万円振り込まれた。わたしはただ単に同じ取材者のよしみで協力してやったつもりだったから、再び萎えた。
高木をネタに原稿も書かずに儲けた1万円は、高木には申し訳ないとは思いながら、確か夜の街で飲んで使ってしまった。いや、国内トップフォーミュラ初優勝を祝って六本木で随分高価な牛タンを奢ったときに還元した、ということにしておこう。