本文:
真夜中のサンマリノGP中継が終わった。居間のサイドテーブルに置かれたマイヤーズの瓶は半分ほど空いている。ぼくはグラスを手に持っていたけれど、その中の氷はすでに溶けてなくなっており、中途半端な色をしたラムが底に溜まっていた。
「いい年して、エフワンなんて、なにがおもしろいのよ」と彼女は言った。「夜中に2時間もクルマが走り回るのを眺めて。そんなことをしている場合じゃないでしょう」彼女はもどかしげに自分の手の中のグラスをゆすった。彼女はグラスから一口もラムを飲んではいなかった。
実はその晩、ちょうどサンマリノGPのフォーメーションラップが始まろうとする直前、どさくさまぎれに彼女に告げていた。「会社、辞めようと思ってる」
フェラーリのお膝元で大ファンのジャン・アレジが初優勝するのを楽しみに、大好きなマイヤーズとソーダをいそいそとサイドテーブルに運んで観戦態勢を整えた彼女は、ぼくの宣言を聞いた途端、目をTVの画面から離さないまま絶句した。我が家の居間を奇妙な沈黙が充たし、レースのスタートに向けて高まるTVの音声だけがそこに響いた。
サンマリノGPがスタートした後も、ぼくたちは黙ったまま過ごした。ぼくは何度かグラスを空けマイヤーズを注いだが、彼女は最初の一杯に口をつけようともせず、レースの展開を理解しているのかどうか、ただTVの画面を見つめていた。
レースが進み、ファイナルラップを迎えようという頃になって、ようやく彼女が口を開いた。すでにアレジはコースの上から姿を消し、アイルトン・セナが淡々とゴール目指して走っていた。
「会社を辞めて、どうするのよ」
彼女は意地を張るように目を画面から離そうとしない。それはぼくにとって有り難い話だった。ぼくもうろたえることなくファイナルラップの様子を観ていられる。
「フリーランスになる。システムエンジニアでもテクニカルライターでも、なんでもやるつもりだ」セナの独走を眺めながら、ぼくは答えた。
「会社にいては出来ないこと? なぜフリーにならなくちゃいけないの?」
セナ嫌いの彼女もまた、白と赤に塗り分けられたフォーミュラカーが淡々と走るのを表情も変えずに見つめていた。チェッカーは振られた。セナの開幕3連勝。今シーズンは、なんてひどい展開になっちまったんだろう。
「できるかもしれない。でも、ひとりで仕事をやりたいんだ。ひとりでやるのがぼくの性に合っていると思う」
「やってみたいっていうのね? それが夢だった、なんて続けるつもりなのね?」
彼女は横目で画面をつまらなそうに眺めながら、薄まってしまったラムにようやく口をつけた。でも、グラスの中身を紅茶にすり替えていたとしても、たぶん気がつきはしなかっただろう。画面ではゲルハルト・ベルガーが2位でフィニッシュする光景が映し出されていた。また、2位だ。今日こそは勝つかと思った。でも、また2位だ。
「夢だったさ。でも踏み切れなかった。昨日、電車を降りるときに決意したんだ。まるで目の前の霧が消し飛ぶような気がした」
「バッカじゃないの」
たたみかけるように彼女が返した。
「アタマのネジが緩んでるわよ。何が大事で何が大事じゃないのか、見えないんじゃないの」
グラスの氷が溶けてしまったのが気になったが、とても冷蔵庫まで氷を補給しに立つことはできなかった。その前になんとか事態を収めなくてはいけない。
「自分が納得できる仕事がしたいんだ」
「あなた、きっと失敗するわよ」
彼女はまたたたみかけてきた。ぼくはマイヤーズをグラスに注ぎ、濃いまま一口なめた。
「万が一失敗しても、納得できれば幸せになれると思う」
「なに若いこと言ってるのよ、十年遅いでしょ」彼女は苛立っていた。
画面ではなんと予想だにしなかったJJが3番手でチェッカーを受けようとしていた。評判倒れのまま、もう駄目になってしまったのかと思っていた。今回のレースの唯一の救いだ。JJは、フィニッシュしながら嬉しそうに腕を突き上げ、ピットの方へ向けて何度も振り回した。観ていたぼくも、自分の置かれた事態を忘れて嬉しくなった。そして思わずぼくは、「一生に一度でいいから」と言った。「一度で言いから、こうやって君に向けて手を振ってみたいんだ」ほとんどドサクサまぎれだった。
それを聞いた彼女は、視線をぼくの方へ送らないまま飲むでもなく飲まないでもなくラムのグラスに口をつけ、そして黙り込んだ。TVの画面は入賞者の会見の様子へと切り替わった。優勝したセナ。またもや2位に入ったベルガー。そして顔を輝かすJJ。ぼくたちは黙ってTVの画面を見つめた。
番組が終わり、居間に静寂が戻ってきた。彼女は区切りをつけるようにグラスをもう一度口に運び、グラスをテーブルに置くと言った。
「いい年して、エフワンなんて、何がおもしろいのよ」
ぼくには返す言葉が見つからなかった。本当だ。ぼくは何がおもしろくてこんなものを観ているのだろう。多分、ぼくはF1を観て自分の身体の中にもまだいくばくかのパワーや可能性が残されているんだということを思い出そうとしているんだ、とかなんとか咄嗟に思ったけれど、気恥ずかしくて口には出せなかった。言葉を失ったぼくをよそに、彼女はしばらく黙り込んだ。そしてそっぽを向いたままつぶやいた。
「手、振ってくれるんだね」
ぼくは慌てて無言のままうなずいた。それが見えたかどうか、彼女は黙ったままグラスのラムを飲み干した。それから意を決したように立ち上がると、ぼくに確かめもしないでTVの電源を落とし、呆然とするぼくを居間に残したまま歩き出して、寝室に籠もってしまった。
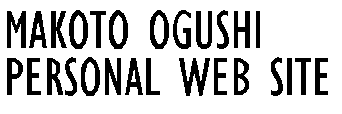
『1991年サンマリノGPの夜』
解説:
1991年初頭に創刊されたF1専門誌、「F1 CIRCUS」の第2号に寄稿したフィクション。事情があって創刊準備や企画から手伝い、誌面には通常のF1記事を書く一方、勝手にこんなものを載せるスペースを作ってチマチマやっていた。国内と海外を週毎に行ったり来たりして仕事をしていた、ハチャメチャに忙しい時期のこと、何か息抜きが欲しかったんだろうと思う。