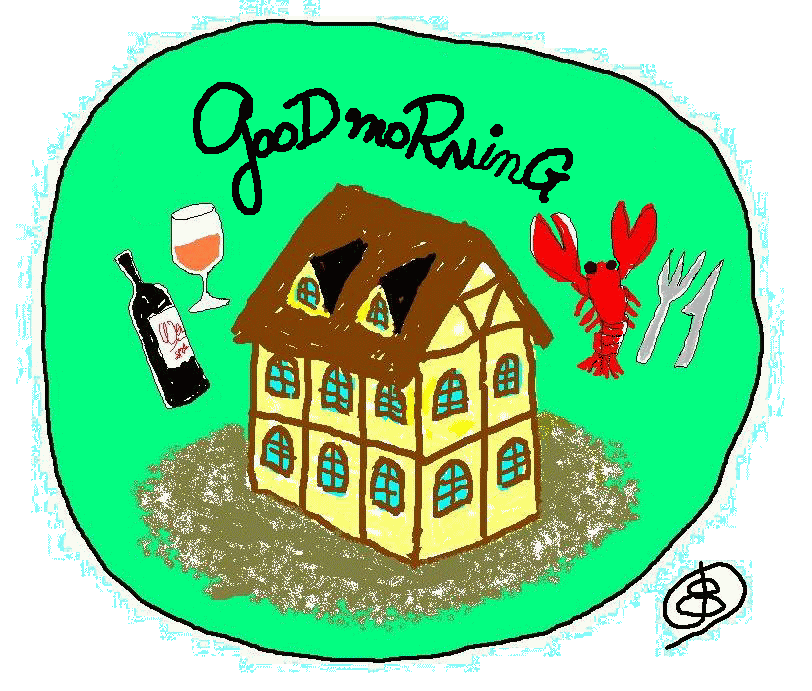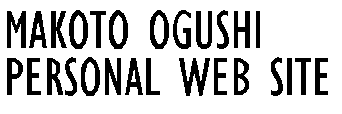
解説:
発表したかどうか、したにしてもどこに発表したか定かではない原稿。ファイルのタイムスタンプは97年はじめになっている。F1ベルギーGPが開催されるスパフランコルシャンのホテルのお話。アベック旅行うんぬんという記述があるが、念のため言っておけば、今の結婚以前の話だ。
本文:
かつてスパフランコルシャンに、ひどく心地の良いホテルがあった。フランス系の料理人が川辺に建てたホテルで、部屋は10室もない程度、街道からかなり引っ込んだ場所にあったので、知らなければ気が付かないまま通り過ぎてしまうような佇まいだった。
ホテルというよりも、民宿のようなその建物に入ると、細かいインテリアだとか飾り付けから、お客様を迎えるのが嬉しくて楽しくてしかたがない、という気持ちが伝わってくる。こうしたインテリアは、主人である料理人の、ひどく美人の若い奥さんが担当したものだった。というよりも、その他の使用人はほとんど姿を見なかった。
主人たる料理人の方は、どうやってこんなに若くて可愛い奥さんをとっつかまえた、と問いただしたくなるほど木訥なオヤジだった。だが料理はうまくて、食べたいものを注文すると、それにきわめて近いものを、ベルギー料理にして食べさせてくれた。生け簀というか水槽に泳がせていたオマール海老を指さして「今夜はこれを食べさせて」と頼んだときも、我々の口にあう見事な味付けで供してくれた。
なぜそのホテルに日本人が出入りするようになったかというと、ある年のグランプリで、周囲のホテルが満室になって困り果てたある日本人カメラマンが、やみくもに走り回った挙げ句、道行く人に紹介されてたどりついたという話だ。確かにそれでなければ、東洋人が踏み入れるような場所ではなかった。そもそもF1グランプリ開催中で周囲のホテルが満室の中で空いていたというのだから、欧州人ですら見つけ出すことのできないロケーションだったのだろう。しかしそのわりには静かで素晴らしい環境に建つ、かわいくて快適なホテルだった。
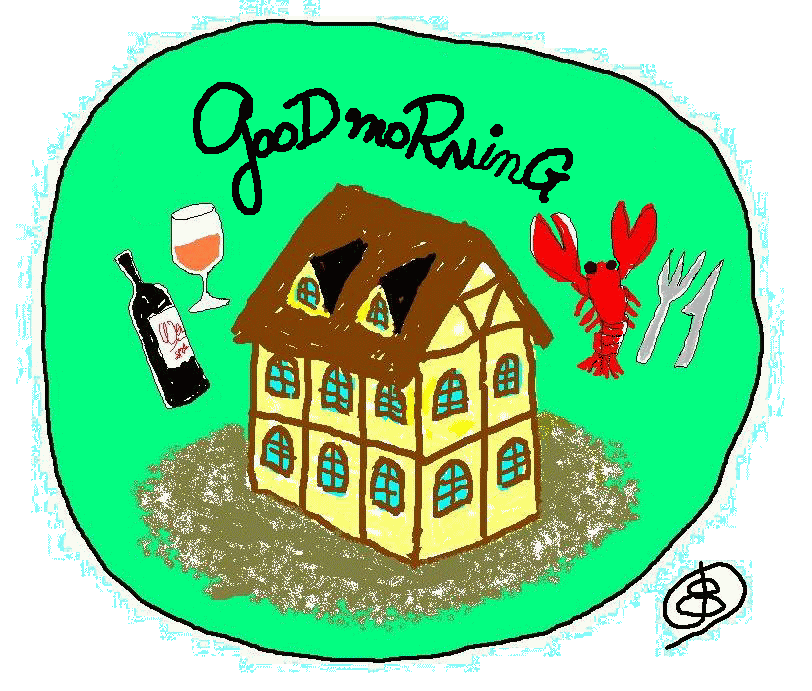
素晴らしいのは環境や設備や料理ばかりではなかった。というよりも我々が最も気に入ったのは、宿の夫婦の人柄だったのだと思う。この夫婦、東洋から来た得体の知れない男どもを、一所懸命お客としてもてなしてくれるのだ。なにしろベルギーの山奥のホテルだから、日本人が泊まるのは初めてだったに違いない。それ以来、F1の時期になってくる我々が行くのを、毎年楽しみに待っていてくれた。
我々が食事を終えてロビー(というよりも、居間といった風情の空間なのだが)でくつろいでいると、仕事を終えた夫婦が身振り手振りで話に加わってくる。前の年に我々と撮影した写真だとかなんだとかをまとめたアルバムが作ってあって、それを見せてくれたりするわけだ。主人は我々に飲み物を作ってくれ、それがおいしいと言うと、「この酒を使ったカクテルだ」とあれこれ説明してくれ、しまいには「いらない」と言うのに、いくつか酒のミニボトルをもたせてくれたりした。
そのうち写真と身振りじゃ足りなくなった彼らは、外国人である日本人ともっとコミュニケーションをとるためには、言葉だ! ということに気が付いたらしい。そこで、勉強を始めたのが、なんと英語だった。 彼らが日常使っていたのがフランス語だったかフラマン語だったかは記憶にないが、当初彼らは基本的に英語をまったく理解しなかった。おそらく、我々が出入りするようになるまで、英語のエの字も使ったことがなかったのだろう。日本語はさすがに無理だが、英語ならなんとかなるんじゃないか、と彼らは考えたらしい。
ある年行くと、奥さんがなにかと英語を使う。しかし、これが微妙にズレていて、なんとも微笑ましかった。奥さんが得意だったのが「グッドモーニング」で、午前中の呼びかけはすべて「グッモーニン」だった。たとえば、朝の食卓で顔を合わせて「グッモーニン」はいい。だが食べ終わって部屋に帰る我々に向かっても、またもや「グッモーニン」とくる。さらにその後仕事の支度を整えてサーキットに向けホテルを出るときも「グッモ〜ニ〜〜ン」と手を振って送り出してくれるのだ。確か仕事を終え夕方ホテルへ帰ってきた我々を迎えるときも「グッモーニン」ではなかったか。
実は奥さん、若い上にかなりの美形であったから、この心のこもりながらも少々ズレたグッモーニンを聞くと、朝っぱらから力が抜けることおびただしかった。日本人は、欧米人はみんな英語が使えるものと思っているフシがあるから、英語の使えないガイジンと言う存在がことさら不可思議に見えた。結局、ぼくたちはこの奥さんに面倒を見てもらう一方、空いた時間にはカタコト英語を教えつつ奇妙な1週間を送ったものだ。
伝え聞くところによると、このホテルは90年代の半ばには営業をやめてしまい、気の良いベルギー人夫婦はどこかへ転居してしまったようだ。残念無念。絶対そのうち、グランプリのない時期に、アベック旅行してやろうと思ってたのに。朝、川のほとりの食堂で、むくつけき野郎どもではなくてちょっとした女性と食卓を囲んだらどんなにシアワセな気分を味わえただろうか。それはともかく、あの夫婦はどうしているのかなあ。おそらくはどこか街のレストランで雇われるかなにかして暮らしているんだろうが、奥さんは英語、うまくなったかなあ。もしどこかで出会って、出会い頭にグッモーニンとやられたら、なんだか胸が熱くなってしまうかもしれない。
『グッモーニン・ホテル』