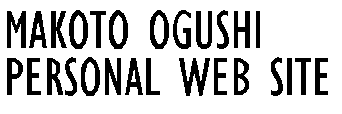
解説:
昨年、父親が死んだときのことを、何より自分のために記録しておこうと思う。ということで書き下ろしである。あれから早1年半、そろそろ記憶が怪しくなり始めている。おそらくこの文章を軸に、少しずつ物事を思い出し、そのたびに手直ししたり追加したりすることになるだろう。
本文:
逗子通信でも一部書いたけれども、父親は実に不思議な死に方をした。友人知人に聞くと肉親の死には大なり小なりこうした不思議な事象がついて回るものらしい。
■親不孝会議
木曜の晩、危篤になったと聞いて慌てて病院に飛んでいった。高速道路を突っ走りながらわたしはかなりうろたえていたが、それは父親が死にかかっているからではなく、山積した仕事の先行きが見えなくなってしまったからだった。これは日記でも書いた。病院に到着してみると、父親はほとんど死にかかってはいたが容態は一時安定していた。わたしは医者の指示に従って、病院そばの実家へ引き上げた。
実家では早くも父親の葬儀の段取り会議になった。わたしは土日と鈴鹿取材の予定があり、その後も原稿の締め切りが重なっていて、葬儀のために動けるのは月曜、火曜、その他の日だとあまり役に立てない、と自分の都合を主張した。東京から駆けつけた実姉は実姉で、息子と娘の大学の卒業式が週明け火曜、木曜と立て続けにあり、どちらにも出席したいから、日付次第ではあまり葬式の手伝いはできないと言う。「じゃあ月曜がちょうどいい」親不孝にもほどがあるが、これが我が家の家風でもある。
翌金曜、病院へ行くと父親の容態はいくらか好転したように見えた。土曜日、わたしはもう一度病院へ出向いて父親の様子を確かめ、思い切って鈴鹿取材に出かけることにした。病院には母親、実姉、女房と出かけた。父親は眼は開けるものの意識はここにない状態ではあったが、眼にはいくらか生気が戻っていた。わたしは、様々な管がつながれた状態の父親に、生前の父親が最も喜んだセリフで呼びかけてみた。「聞こえるか〜? 儲かってるぞ!」と。まあ、零細自営業者としてはウソも方便というやつだが。
すると父親の表情がわずかに緩んだ。どこまで理解できたのかはわからないが、脳が「心地よい音が聞こえた」程度の認識はしたのだろうと思う。だがそれ以上の反応は起きなかった。わたしは医者の「延命策は患者を苦しませるだけだからやめよう」という提案を受け入れていた。正直なところ、生きている者の都合ではあるが、希望のないままただ生きているだけという状態を維持していくだけの体力や時間や資金力が自分にあるとは思えなかった。そういう事情を無視して強引に父親を生かし続ける意味はないし、医者の言うとおり無意識の中であるにせよ父親を苦しませたくもなかった。無情に聞こえるけれども、この数年のうちに、正常な会話は不可能になるまで父親の痴呆は進んでいた。その過程で、すでにわたしもその他家族も、緩慢な死を感じ取っており、危篤状態は自然に訪れた締めくくりの段階でしかないと覚悟ができていたからだと思う。
■最後のバイバイ
わたしは、1泊2日の取材旅行中に容態が急変する可能性も考えた。たとえば土曜日夜中に知らせがあっても、身動きはとれない。確かに自分のクルマで行くとかタクシーを使うとか道はあったのかもしれないが、そこまで用意する気もなかった。ただ、帰ってくるまではなんとか生き続けていてくれよ、とは祈った。そして病室を出ようとしたときだ。背後から母親や姉や女房に「待って、待って!」と呼び止められた。びっくりして振り向くと、それまでまともな反応を示さなかった父親がこっちを向き、毛布の下からやっと右手をのぞかせて手を振っていた。
驚いた。本当に驚いた。わたしはまた父親のところまで戻ったが、特に意識が戻っているわけでもなかった。「無意識のうちにバイバイってやったんだよ」と家族でしみじみすると同時になんだか嬉しくなった。少々希望的観測ながら、これならまだ、しばらく大丈夫だなあとわたしもどこか安心した。だが、これが父親と最後の別れになった。
わたしはその足で新幹線に乗り鈴鹿に入った。土曜日の晩は、友人と鈴鹿は平田町の居酒屋で飲んだ。終電で帰ることのできる時間まではとりあえず正気を保ち、「もう帰れないな」という時間を見て、わたしは酒を煽った。メニューには載っていなかったが、わたしの大好きな大分の酒、西の関が棚の隅にあるのを見つけ「それ飲ませて!」と偏屈な店のオヤジに頼んで飲んだことを覚えている。
結局恐れていた知らせは届かず、わたしは翌日軽い二日酔いを感じながら取材現場に出かけた。しかしさすがに気持ちはそぞろ、レースフィニッシュと同時に友人とタクシーに乗って早々に帰路についた。新幹線を乗り継いで大宮に着いたのは午後8時前だったか。そこでわたしは妙な胸騒ぎを覚えた。大宮から実家へ直行するなら東武野田線、父親の病院に寄るならば東北本線、どちらも目的地までの所要時間はそれほど変わらない。わたしは大宮駅のコンコースで一瞬迷ったが、女房と電話で話した際に「昼間、病院に行ったがお父さんは小康状態だった」という言葉を思い出して、実家へ直行することに決めた。実家では母親と女房が、なぜか酒盛りの用意をして待っていることになっていた。結局はみんな父親の死を待っているのだ、酒でも飲むしかやることはない。
■ビールを一杯
白岡町にある実家には9時前に着いた。母親、女房と食卓を囲み、缶ビールを開けて3人で乾杯をした。グラスにあけたビールの一口目を口に含んだとき、電話が鳴った。「またぁ〜。TVドラマじゃないんだからさ〜」というタイミングで鳴った電話は、案の定病院からで、父親の容態が急変したのですぐに来い、との知らせだった。「もしこのまま父親が死ぬのだとしたら、まるでわたしが仕事から帰ってくるのを待っていたようなタイミングではないか。しかも酩酊しないよう、ビールを一口だけ飲ませてくれたというタイミングではないか」とわたしは驚いた。
タクシーを呼ぶ時間は待てない。ビールを飲んではいたがひとくちだ、ごめんなさい、だって父親が死んじゃうんだ、と駐車場のクルマに3人で向かった。10分ほど走って病院に駆け込んだのは9時半。病室へいくと、父親が医師と看護士に囲まれて寝ていた。当直だったらしい女医の言動は、今思い出しても首を傾げるほど怪しかった。モゴモゴと経過を語り続けるが、今、どういう状態なのかを言わない。だが、雰囲気はどう考えても終わっているのだ。わたしは苛立って「で、要するに死んじゃったってことなの?」と聞き返した。すると「はい、そういうことになります」と答えたもんだ。あの医者、一体なんだったんだろうか。
わたしはそれを聞いてオヤジの額をなでてみた。まだ暖かみが残っていた。思わず「ご苦労様でした」と言葉が出た。おやすみなさいでもさようならでもあるまい。本当はなんと言うべきだったのかなあと後から思ったが、まあいいところだっただろう。母親が「臨終は何時ですか」と女医に尋ねると、彼女はその場で腕時計を見て「ええと、9時27分…です」と答えた。まあ、おそらく当直室でみんなでバカ話をしていたら、誰かが父親の脈が止まっていることに気づき、慌てて病室に駆けつけたら死んでいた、というところなのだろう。確かに我々にとってはたったひとりの男ではあったが、他人にしてみればその程度の存在でしかないのも事実。素っ気ない扱いに、とりたてて目くじらを立てる気は起こらなかった。
■もう死んでます!
そもそも、我々も我々だった。ひとしきり病室で父親の死を悼むと、わたしも母親も、スイッチが切り替わったように、今度は「葬儀の段取り」に入った。父親のベッドから立ち上がり振り向くと母親が葬儀社のパンフレットをわたしに差し出す。なんと、準備のいいことだ。それを持って、階下の待合室へ行き公衆電話で電話をかけようとすると、待合室の照明が落とされていてうす暗く、老眼の始まった目では細かい電話番号が読みとれない。しかたがないのでそこにいた女房に電話を頼んだ。
ところが後になってわかったことだがこの時点で女房はまだ父親が臨終を迎えたことを知らなかった。と言うのも、病院に到着した時点で「これは大変だ」と、女房は病室を飛び出し杉並の実姉の家へ電話をかけに走ったからだ。わざわざ病院の外まで行って携帯電話を使い、実姉に連絡を取り戻ったところでわたしに出くわし「葬儀社に電話を!」と言いつけられた女房は、「亡くなる前に葬儀社に電話してもいいのかな」と内心思いながらダイヤルをしたという。
それも今思えばナニなのだが、電話に出た葬儀社の係員に「亡くなったんですね」と確認された女房は「いえ、まだ亡くなってません」と答え、「こちらに電話するのは亡くなってから…」と諭され、振り返って「亡くなってから電話してくれと言ってるよ?」とわたしに言う。後ろに立っていたわたしと母親は別に慌てることもないのに慌てて「死んでる!死んでる!」と怒鳴る。それでまた慌てた女房が電話に向かって「すみません、もう死んでました!」と伝える。もう笑い話になっていた。
わたしは、最後の別れをこんな笑い話にしてくれた父親に感謝している。父親は、少しずつ少しずつ、わたしたちと別れていってくれた。しかも、最後に最も近しい親族に手まで振ってくれた。しかも、わたしが仕事から帰ってくるのを待っていてくれた。しかもビールを一口だけでも飲ませてくれた。しかも、わたしと姉の都合を考えたかのように、まるでスケジュールの空きをピンポイント爆撃するようなタイミングで逝ってくれた。ほとんど意識がないまま、そもそも自分の死期をコントロールすることなどできないはずなのに、今考えても不思議でならない。
■通夜の大宴会
月曜日に集中してあれこれ葬儀の準備ができたので、火曜日の午前中は原稿を書くこともできた。父親の葬儀は、様々な方の協力や志をいただいて、盛大に執り行うことができた。予想もしなかった規模に、母親は父親の死を悼むことも忘れて大喜びしてしまい、父親の棺の前でしなを作って記念撮影をせがむ始末だ。通夜の席は、元来お調子者の多い大串の親族が久しぶりに集まってしまったものだから、笑い声に溢れる大酒盛り大会になり、現場に居合わせた甥が困惑して、喪主であるわたしに「なんだか忘年会みたいになっちゃったね」と耳打ちするに至った。まさにこれ天寿を全うした父親の人徳の賜物、臨終に続き、まことに父親らしい見事な締めくくりである。
大声でケラケラ笑いながら「じゃ〜、まったねぇ〜」とタクシーの窓からご機嫌で手を振り別れの挨拶を残して去っていった親戚を見て、斎場の係員も苦笑をする始末だったが、それを係員と並んでやはり苦笑しつつ見送ったわたしは救われた気がした。自分自身はともかく、心配だったのは遺された母親の気持ちだったが、どちらにせよ父親の死を何らかの形で受け入れなければならないのだとしたら、誤魔化しかもしれないけれどもこうやって陽気に騒いで葬式を終わらせてしまえば、その後はなんとかうまく軟着陸できるのではないか、と。そして結果的に、わたしが願う形で少なくとも表面上は、父親の死が既成事実として母親やわたしの生活の中にすんなりと収まることになった。

■不思議な遠回り
翌日告別式を終え、父親の亡骸を乗せた霊柩車の助手席に喪主として位牌を持って座った。座りながらわたしは「こういうときはシートベルトをしなくていいんだろうか」と、そればかりが気になってちらちらと運転手を伺ったが、運転手もベルトはしていなかった。「霊柩車のシートベルトというテーマで1本原稿が書けるかもしれないなあ」とわたしは商売のことを考えたりした。(実際その後原稿を書き、原稿料を手にした)
霊柩車はしずしずと走り始めたが、なぜか運転手が途中で火葬場への道を間違えて、かなりの遠回りをすることになった。運転手は運転しながら平謝りしたが、わたしは不思議な気分に包まれ、むしろ遠回りを感謝したい気分になっていた。というのも遠回りの頂点にあったのは、生前の父親が足繁く通ったゴルフ練習場であることに気づいたからだ。今思っても不思議だが、まるでわざわざそこを通り過ぎるために間違えたような道だった。
父親の棺を火葬場の炉の中に納めたとき、何度か想定はしてはいたものの、これが最後の別れかとしみじみした。最も慌てたのは、1時間ほど経って、喪主としてひとり呼ばれて焼き上がった父親の遺骨の確認をしたときだ。父親は、何かの標本のように、おおよその身体の形が判る状態で骨になっていた。想像もしなかったその光景に虚を突かれ、ああ、本当に自分は父親を焼いて骨にしてしまったんだ、と正直うろたえた。もうすっかり父親と別れたつもりでいたのに、実はまだ振り切れないままの思いが残っていたということなのか。
ただし、その後も続いた、骨を拾ったり納骨したりという儀式には、わたしは単なる儀式以外の重みを感じなかった。骨壺に骨が収まりきらないので、係員が我々に断りを入れた上で、壺の上から骨を手で押し込み、骨が崩れる音がしたとき、叔母が「やりきれない」と洩らしたが、わたしは「そうかもしれないなあ」と思っただけだった。もう父親は無機物になってしまった。生前の位置関係を崩して壺に押し込まれた骨は、わたしにとってはもはや父親ではなかったからだ。とりあえず父親をおくった後、わたしと母親と女房は何もかも忘れて見とれるほどに満開の桜並木を通り過ぎて家路へついた。これもまた今から思えばあまりにも出来すぎの光景であった。
『父去りし春』
