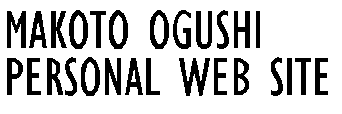
解説:
月刊モデルグラフィックス2000年8月号、「究極のル・マン」特集に寄稿した原稿。モデルグラフィックスは、模型趣味の人間向けの月刊誌で、その(怒られるかも知れないけれども)ヲタク風味な編集方針と作り込みが大好きな雑誌。ときどきレース関連の特集があると声がかかったりする。「模型専門誌」とはいえ、レース専門誌より素材に対する着目点が優れていたり執着があったりで、親しいレース専門誌編集者には「モデルグラフィックスを手本にしたら?」とささやいたりすることもある。で、今回の依頼は「ル・マンについて」であった。ル・マンは大好き、わたしのレース趣味の原点でもある。で、こういう原稿を書いた。
本文:
■本命の陰にキワモノあり。
ル・マン24時間というと、1990年のことを思い出す。走行が始まった水曜日、わたしはユーノディエールに設けられたシケインのコースサイドで、あるクルマがやってくるのを待っていた。
今となっては幻のような話だが90年は、その後フランス人に牛耳られるに至るニッサンが、日本チーム初のル・マン総合優勝を目指し必勝態勢を整えてこともあろうにそのフランスへ攻め入った年である。ワークス5台、プライベート2台総勢7台という物量作戦、その中心となるのは英国ローラ社と共同開発したシャシーにターボ過給V型8気筒エンジンを搭載したニッサンR90C/Kである。ワタシは、かなりの確率でニッサンはその思いを遂げてしまうことになるだろうと思いながらル・マンに向かったものだ。
だが、ワタシがコースサイドで待っていたのはニッサンではなかった。ワタシとカメラマンのお目当ては、アメリカからわざわざ来襲したというふれこみの「イーグル」と名乗る怪マシンであった。イーグルとは言ってもどうやら本家AAR(オールアメリカンレーサーズ)とはまったく関係がないこのクルマ、船舶用エンジンを流用したとかいう自然吸気「10リッター」V型8気筒エンジンを搭載していた。10リッター。随分長いことレースを眺めてきたが、ワタシの記憶にある限りでは最大排気量のレーシングエンジン(なのか?)である。
大艦巨砲主義時代ならともかく90年代グループCカーレースを戦うトップチームは、コンピュータ解析でターボなら3.5リッター、自然吸気で5リッター前後がベスト排気量であるという理論上の解答を出していた。そこに10リッター。常識はずれにもほどがある。だがこうしたキワモノは、ル・マン24時間レースの大きな魅力のひとつなのだ。ぜひとも走っている姿を眺めたい、排気音を聴きたいとワタシは思い、わざわざユーノディエールまで出かけてイーグルが飛来するのを待つことにした。
ところが、こうしたキワモノは多くの場合まともに走らない。件のイーグルも、なんとか車検は通ったもののサーキットに来てからはそのまま出走のための整備というか調整というか修理に入ってしまい、なかなか走ろうとしない。待っても待っても走り出さないので、わたしは待ちくたびれてしまった。いくらなんでもキワモノすぎたかな、と思ったとき。
■鷲は帰らず。
フランス語の場内放送が「イーグルが走り出した」と言っているように聞こえた。コース脇の草むらに座り込んでいたワタシとカメラマンは飛び起きた。「来るぞ!」とコースに目をやる。イーグルは、どんな姿でどんな音を立ててどんな挙動を見せながら走るのか。ワタシの胸はときめいた。
ところが待てど暮らせど、やってこない。確かにユーノディエールは1周13km以上もあるル・マンのコースのバックストレッチだ。俊足ニッサンですらピットアウトしてから姿を見せるまで1分半はかかる。だがイーグルときたらようやく走り出したのはいいが、ほとんど徐行状態でいるらしく、5分経ってもその姿を見せない。「なんだ、こりゃ。止まっちゃったんじゃないのか。いや、そもそも場内放送を聞き違えたかも」とワタシはまたもや待ちくたびれて座り込もうとした。そのときだ。
バロバロと、今まできいたこともない排気音を立てながら1台のマシンがシケインによろよろとたどり着き、まるで捻挫して足を引きずっているかのように方向を右、左と変え、またバロバロと得体の知れない排気音を残して走り(というより歩み)去った。わたしは呆然とイーグルを見送った。なんとカメラマンまでもがファインダーを覗きシャッターを押すことを忘れ、立ち尽くしているではないか。イーグルが見えなくなってはじめてカメラマンは「あ。写真撮るの、忘れた」とポツリとつぶやいた。
イーグルの10リッターエンジンは、なんとも破滅的な排気音を立てた。シリンダーの中で混合気が爆発しカムシャフトが回りバルブが開閉しクランクシャフトが回転する、それだけの音ではなく、どこかで常に何かが壊れ続けているような複雑な機械音だった。そして案の定、やはり何かが壊れ続けていたようで、わたしたちの前を通り過ぎたイーグルはその後コースの終盤にあるフォードシケインあたりで息絶えてしまった。そのトラブルは致命的だったようで、その後イーグルは一度もコースを走ることなくル・マンから姿を消してしまった。つまり、イーグルはせっかくアメリカから飛来したのにル・マンを1周することなくレースを終えてしまったのである。
イーグルが壊れて止まった、とフランス語の場内放送が叫んだのを聞いた我々は、「あー、やっぱりね、あれじゃしかたないね」と顔を見合わせたが、その後でカメラマンがまたポツリとつぶやいた。「てことはもう走りの写真が撮れないんだね」 というわけで当時ワタシが担当したレース雑誌のル・マン記事にはイーグルの写真は掲載されなかった。
■一粒で二度おいしいレース
ル・マン24時間は、F1グランプリと並ぶ世界的イベントとして知られている。実際、ル・マンの勝者となりモータースポーツの歴史に名を残すために、世界の自動車メーカーやレーシングチームがこれまで最先端の技術を詰め込んだスーパーカーを持ち込み戦ってきた。F1グランプリでは近年でこそメーカー戦争が激化しているが、ル・マンでははるか昔からメーカーが格闘してきたのだ。ざっと思い出してみただけでも、フェラーリ対フォード、フェラーリ対ポルシェ、ポルシェ対ルノー、ベンツ対ジャガー、ジャガー対ニッサン、トヨタ対プジョーなど、名勝負は数知れない。
昨年はダイムラーベンツとトヨタが激突した。この2社が投入した活動資金は、おそらく1戦当たりに割り算すればF1グランプリをはるかに上回る規模だっただろう。そこで用いられた技術も、スプリントと24時間耐久というレースの特性の差があって単純な比較はできないものの、かなりの部分でF1グランプリ以上のレベルにあった。最先端の技術を投入して開発されたレーシングカーが集い争う場として、ル・マンはF1グランプリに勝るとも劣らぬ大舞台であることに違いはない。
だが、ル・マンにはそれに加えてF1グランプリにはない魅力がある。それがたとえばイーグルのような泡沫候補の楽しさなのだ。優等生と劣等生がそれぞれの特色を出しながら同じコースで同じレースを戦う。これがル・マンの醍醐味である。優等生だけでも劣等生だけでもこの楽しさは生まれない。メーカーがものすごい物量と技術を振り回して激闘を展開しているそばで、夢と希望と少々の妄想を抱え込んだ泡沫候補が走っている。(あるいは走ろうとしたけれどもエンコしている)ああ、なんと素晴らしい状況であることか。
泡沫候補につられるかのように、最前線で戦うメーカーですら、ル・マンではハメをはずす。70年代のポルシェは917を主戦機種としていたが、ル・マンにしか現れなかった異形のモデルがいくつもある。これがまた楽しい。
F1グランプリにもかつては一部にル・マン的楽しさがあったが、近年ではいやらしくも種の選別が進み、飛び抜けた優等生だけが集まったレースになろうとしている。それはそれでひとつの見せ方ではあるのだが、F1グランプリよりも「自動車レース」が好きなワタシとしては、非常に物足りない。
実はル・マンでもその傾向が強まってはいるが、イーグルほどではないにせよ依然としてキワモノは健在で、ワタシは嬉しい。たとえばパノス。「だってぼく、フロントエンジンのスポーツカーが好きなんだもん」というオーナーの意向で最先端の技術を投入して開発されたはいいが、その姿はあまりにも乱暴だ。でもル・マンカーは、こうでなくっちゃ。そしてル・マンはこうでなくっちゃいけない。誰が言ったか、「偉大なる草レース」。ワタシはもし万が一ル・マン24時間レースが草レースではなくなってしまったら、取材などには絶対に出かけないだろう。

『鷲は舞い上がらず』
